社員に中国語を学ぶ機会を提供したいけど、どんなサービスがあって、どうやって導入をしたら良いのかがわからないという企業の担当者の方も多いかと思います。
そこで、この記事では元大手企業の海外人事担当者が、企業・法人向けの中国語研修プログラムについてどのような種類があるのかを解説・比較します。また、導入にあたって検討すべきことも解説しておりますので、ぜひ最後までお読みいただき、今後の導入の基礎知識を得ていただけると嬉しいです。
【中国語研修導入の教科書】PDFを無料でプレゼント
\知りたいことが全部わかる!/
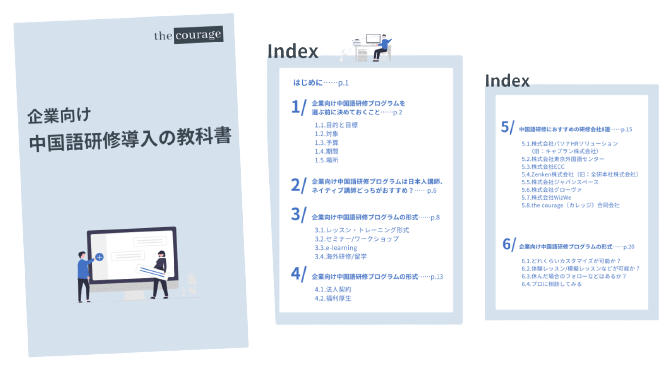
企業向け中国語研修プログラムを選ぶ前に決めておくこと
これは中国語に限った話ではありませんが、企業が研修を導入するうえで確認しておくべきこと、事前に決めておくべきことについて説明します。
目的と目標
まず、語学研修の目的と目標を文言化しておきましょう。
目標については、HSKや中検などの検定試験(英語でいうところのTOEICや英検のような試験)があるので、そちらを基準にすると良いです。目的については各企業の方針が色濃く反映されます。
例えば、以下のような例があります。
具体的業務と直結しているケース
「海外駐在員が駐在期間十分に活躍することで世界で通用する組織にしていきたい」
「これから具体的に中国進出を考えているので、その時に営業ができる人材を今から育てておきたい」
少し中長期的に社の雰囲気を醸成するケース
「すぐに中国との取引は無いけれど、今後英語圏・中国語圏の両方を視野に海外進出を考えているから社員にそうした世界を意識してもらいたい」
このように、今の自社のフェーズに応じて異なる目的があり、その目的を達成するためにどんな目標を設定するかというところまで決めておくと、その他の項目を決める時の判断基準としても活きてきます。
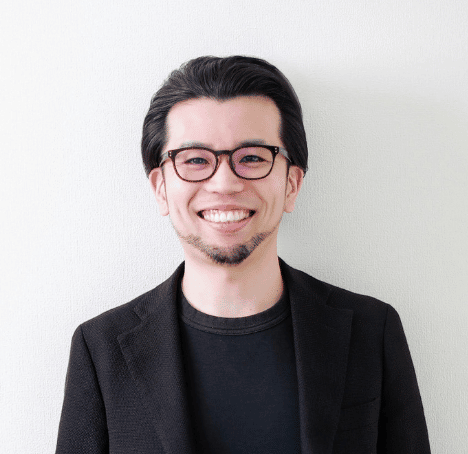
これは資格試験を目指すのか、或いは実際の会話力を目指すのかにも関わってきます。最初は一定の資格試験でインプット量を測り、その後そのインプットされた知識を運用できるかどうかという会話のトレーニングに移るといった全体のロードマップを描けるのがベストですね。
対象
目的と目標がハッキリすると、この対象についても自ずと決まってくることが多いです。
経営幹部や海外駐在員に集中して予算を投下することで使える中国語を身につけてもらうのか、あるいは少しでも多くの社員が外国語を学ぶことで会社全体の雰囲気作りを進めるのかなどが考えられます。
また、会社が指名した社員に研修を提供するのか、希望者に対して提供するのかなども重要な視点です。強制参加の場合と希望者の参加の場合では参加するメンバーの熱量にも差が出ることが多いので、提供するカリキュラムなどにも工夫が必要になってきます。
予算
予算については本当にピンキリで幅があるので、こちらも目的などと照らして決めて行くことがおすすめです。
社員が楽しくゆるやかに勉強するという場合であれば週に1回のレッスンを提供するなどにして、費用もかなりおさえることができます。他にも、e-Lerningをメインにするなどして、一定のクラス品質は維持しながら価格を下げるということも可能ですね。
一方で、海外駐在前の社員の特訓であったり、今後売り上げが見込まれる対中国ビジネスに関わるメンバーへの研修ということですと、それなりの経験がある講師やカリキュラムが必要になるので価格も上がってきます。
期間
期間については、2~6ヶ月という比較的短期で研修を行い、その後卒業するというケースもあれば、数年単位で着実に力をつけていくという方法もあります。
業務上必要という場合には短期集中が選ばれることが多いですが、語学の習得は比較的長い道のりにはなるので、短期集中で実力UPを実現しつつ、その後のフォローまでセットで考えられると良いです。海外駐在員についても駐在前の研修だけでなく、駐在後のフォローまで行うという感じです。
また、雰囲気醸成という意味では年単位で研修内容を決めて、いつでも自由に参加できるようにするという工夫をして成功した企業などもあります。
場所
これはコロナで一気に進んだオンラインでの研修か、あるいはリアル(多くは会社内)での研修かの違いですね。
従業員が全国にいる場合には自ずとオンラインになるかもしれませんが、一箇所に集まって研修が可能という場合にはそこで実施することも可能です。
また、海外駐在員の場合にはすで海外駐在員の駐在前研修などが設定されているケースもあるので、その場合には単発ではありますが、「外国語学習の方法」ということで研修を導入するというのも可能です。
企業向け中国語研修プログラムは日本人講師、ネイティブ講師どっちがおすすめ?
日本人講師とネイティブ講師、どちらにもメリット・デメリットがありますが、一般的なケースを想定すると、中国語は英語と違って基礎知識がないことがほとんどです。
そのため、文法の説明、勉強方法の説明などを日本語で行う方が、中国語で実施するよりも遥かに効率的です。
なので、日本人かどうかということではなく、仮にネイティブであっても、日本語でそうした内容を詳しく説明できる講師がおすすめです。
また、すでに学習が進んでいる中上級者に対しての研修ということであれば、中国語を学んだことがある日本人講師と、ネイティブらしい表現なども分かるネイティブ講師のハイブリッドなどが理想的です。
更にすでに中国語で業務を行っている上級者であれば、会話の機会を提供すると同時に、各シーンで適した表現なども知る必要があるので、そうしたことまで説明ができるネイティブ講師がおすすめです。
- 初心者:文法や勉強の方法などを日本語で詳しく説明できる講師
- 中上級者:日本人講師とネイティブ講師のハイブリット
- 上級者:適した表現を説明できるネイティブ講師
【中国語研修導入の教科書】PDFを無料でプレゼント
\知りたいことが全部わかる!/
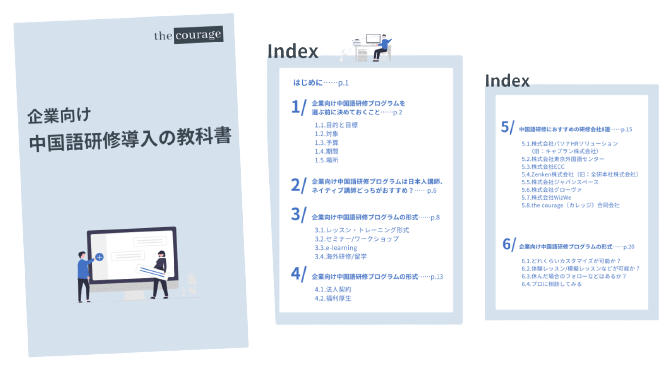
企業向け中国語研修プログラムの形式
中国語研修プログラムについては様々なケースががあるので、それぞれの特徴やメリット・デメリットを紹介します
レッスン・トレーニング形式
レッスン・トレーニング形式
一番最初にイメージする研修形式はレッスン・トレーニング形式ではないでしょうか?
先生が中国語を教えたり、中国語のトレーニング方法を教えるというもので、対面・オンラインで学ぶ学校の授業のような形式です。
レッスン・トレーニング形式のメリット
レッスン・トレーニング形式のメリットは、実際に講師とのリアルタイムでのコミュニケーションがあることから、参加者のモチベーションが保ちやすく、その場で質問などもできることから迅速な疑問解消ができるので、学習効果を高く保てるというメリットがあります。
レッスン・トレーニング形式のデメリット
一方でデメリットとしては、一人の講師につき対応できる時間や場所、人数が限られるので、研修の参加人数が増えるとコストがかかるだけでなく、質のバラツキが出てくるなどのデメリットがあります。(これは研修会社の講師確保の問題でもありますね)
レッスン・トレーニング形式にする場合に検討するべきポイント
レッスン・トレーニング形式にする場合、検討するべきポイントは3つです。一つずつみていきましょう。
- 対面かオンラインか?
- ティーチングかコーチングか?
- マンツーマンかグループか?
対面かオンラインか
対面ですと緊張感を保つことができたり、講師と同じ空間を共有することでグループワークがやりやすいなどのメリットがあります。
オンラインではどこにいても受講ができ、チャットツールを駆使したり、録画を活用することで対面よりも高い効果を感じるケースも多いです。ただ、講師がオンラインのレッスンに慣れている必要があります。
ティーチングかコーチングか
ティーチングは先生がその知識を使って中国語について、分かりやすく説明してくれるスタイルで、いわゆる学校で英語を習った時のようなやり方です。
一方でコーチングは中国語を教えるのではなく、中国語の勉強方法を教えて、それをやり抜くためのサポートまで実施するスタイルです。ダイエットで有名なライザップのようなパーソナルトレーニングと似ていると感じる人も多いです。
中国語コーチングのthe courage(カレッジ)では元海外人事の経験もあるキャリアコンサルタントが丁寧にヒアリングをしたうえで、企業の目的に合わせた研修プログラムを提案させていただきますので、ぜひ一度相談してみてください。
マンツーマンかグループか
マンツーマンであれば、講師が一人ひとりの状況をよく把握することができます。グループであればそうしたきめ細やかなサポートは薄くなるかもしれませんが、チーム全体で頑張ろうという雰囲気でマンツーマンよりも効果が出ることもあります。また、一般的に一人あたりのコストはマンツーマンの方が高いです。
セミナー/ワークショップ
セミナー/ワークショップ
継続的にレッスンを行うのではなく、数時間~数日のまとまった時間の中で、可能なレクチャーを行うのがセミナー/ワークショップです。
セミナー/ワークショップのメリット
短時間でまとまった知識をインプットすることができるので、短期間で中国語学習の全体像を身につける、或いは本当に基本のフレーズを覚えるなどができます。その日だけ頑張ればちょっと使える知識が身につくというのがメリットです。
セミナー/ワークショップのデメリット
一時的な効果にとどまり、継続的な学習に繋がらないことが多いので、明確な成果を期待しにくいということ、また、従業員の比較的まとまった時間を拘束することになるというのがデメリットです。
e-learning
e-learning
パソコンやスマートフォンを使って動画を視聴し、場合によっては視聴後に簡易テストを受けて実力がついているかどうかを測定するというスタイルの研修です。
e-learningのメリット
いつでも自分のペースで研修を受けることができ、何度でも繰り返し視聴することができるというのが最大のメリットです。その他場所を選ばす、コストを下げることもできます。
e-learningのデメリット
自分のペースで価格を下げて受講が可能ですが、その分受講者の意志に頼る部分があります。やらない、あるいはやってもいい加減に再生だけしてしまうことなどが発生する可能性があるのがデメリットです。
海外研修/留学
海外研修/留学
中国の大学には語学留学を受け入れる専門の学科があります。語学学校が大学に付属しているようなイメージですね。そのため、中国の大学で中国語を学ぶということが可能です。
海外駐在員が駐在後の半年はこうした大学での留学をするケースも多く見られます。終日学校に通うケースもあれば、半日は学校に行き、半日は仕事をするケースもあったり、期間もまちまちです。
海外研修/留学のメリット
やはり現地で生活しながら、基本的には中国語にどっぷりと浸かることになるので、日本で仕事をしながら学ぶのと比べると習得度はかなり高くなります。
海外研修/留学のデメリット
一般的な留学と近い形なので、基本的には現地で生活までする必要があり、語学研修の費用だけでなく、渡航費や居住費なども発生します。
企業向け中国語研修プログラムの導入形態
法人契約
法人としての契約は以下のパターンがありますが、②については個人で支払いまで行い、後から精算という形で対応することが多いです。
- 法人として研修会社と契約を結び、社員がそのプログラムに参加するというケース
- 社員個人が一般のスクールを探し、会社に申請して、認められたら通うというケース
福利厚生
福利厚生として、指定のプログラムであれば会社が補助を出すというケースもあります。
中国語研修におすすめの研修会社8選
株式会社パソナHRソリューション(旧:キャプラン株式会社)
-1024x423.png)
2023年10月からパソナグループの子会社で人事BPOサービスを展開する株式会社パソナHRソリューションと合併していますが、それまでにも語学やカルチャーなどの人材教育事業を展開している実績のある会社です。中国語ネイティブによる中国語研修で、少人数制が特徴です。
・おもてなしランゲージ®中国語研修
中国語の基礎である声調や発音などを学んだ上で、接客で使うフレーズや表現を学ぶことができます。(お客様の受け答え、お詫び、商品のおすすめなど)
また、宝石や素材などの特殊な単語や表現などを、学ぶことも可能です。
対象者:接客に携わるスタッフ、現場管理職
研修時間:~30時間
人数:4~6人
企業サイトはこちら:https://pasona-hrs.co.jp/
株式会社東京外国語センター

東京外国語センター(TCLC)は昭和37年から外国語の総合コンサルタントとして、多くの企業・団体のコミュニケーション能力開発をサポートしている実績があります。企業向けに「工場の中国語」など、企業の現場ですぐに必要となる力を身につけることも可能なプログラムがあります。
・赴任・出張前中国語研修
中国語の基礎を学び、現地の生活において、必要最低限のコミュニケーションを身につけることができます。
研修時間:20~80時間
・工場の中国語
現地の工場の現場で初歩的なコミュニケーションがとれることを目的としたプログラム。手順の説明や確認の表現から、けが病気などについての表現も学びます。
研修時間:60時間
企業サイトはこちら:https://tclc-web.co.jp/
株式会社ECC

企業ではない一般向けの事業も展開しているので、英語では名前を聞くことが多いかと思いますが、ECCも企業向け中国語研修を行っています。中国出張や赴任でよくある場面を設定したカリキュラムを使用し、全10課で完結する体系的なトレーニングを実施することができます。グループレッスン、マンツーマンレッスン、海外赴任前短期集中レッスンの3種類から選択することができるので、ニーズに合った研修を選択できます。
※用意されたコースはなく、ニーズに合った研修が可能。
中国語初心者向けのコースで、グループ、マンツーマン、海外赴任前短期集中から選べます。必要に応じて、時間や回数などの設定が可能で、目安として最大30時間。
出張や赴任先でよくある場面をテーマとし、発音、単語、文法やフレーズなどを学ぶことができます。
企業サイトはこちら:https://www.ecc.co.jp/
Zenken株式会社(旧:全研本社株式会社)
-1024x483.png)
「世界で戦える人材育成」を目的とした英会話研修事業「リンゲージ」を運営する会社で2023年10月1日より、商号(会社名)を「全研本社株式会社」から「Zenken株式会社」に変更。中国語に限らずグローバル人材育成が可能なので、日本語研修など、その他言語研修と併せての依頼も可能です。
・中国人講師の派遣レッスン・ビジネス中国語
中国との文化の違いや中国社会を理解した上でのコミュニケーションスキルを身につけることができます。
対象者:中国人とのビジネスを予定している方
研修時間(推奨):80時間(2時間×40回)
人数(推奨):8名程度
企業サイトはこちら:https://www.zenken.co.jp/
株式会社ジャパンスペース

実践的対話力を身につける中国語教室「ショーバ」を運営する株式会社ジャパンスペースは企業向けの研修も行っています。企業研修ニーズヒアリングと受講者のレベルチェックを総合して、カリキュラムを組めるだけでなく、e-learningで予習をして授業をより効果的に行うということもできます。
・発音基礎講座、基礎中国語会話(初心者)
・総合中国語会話講座(初級~上級)
・ビジネス会話講座(中級・上級)
それぞれ中国語のレベル、職種、期間に合わせたカリキュラムです。
レッスンは会話のトレーニングが中心のため、可能な限り中国語だけのレッスンができるよう、e-learning予習の活用、カタカタ読みの禁止などの習慣づけを行っています。
企業サイトはこちら:https://www.shuoba.jp/
株式会社グローヴァ

企業向けの中国語研修提供で多くの実績を持ち、豊富な研修内容が魅力です。一般的な中国語研修だけでなく、出張・赴任者向けの「サバイバル中国語レッスン」の提供も可能です。翻訳・通訳事業も展開しているため、研修以外にも専門分野の資料翻訳依頼もできます。
・サバイバル中国語研修
中国滞在での必要最低限の知識と中国語力を短時間で学べる講座です。
中国語での自己紹介や日常的な挨拶などを学ぶと共に、異文化理解のセミナーもセットになっており、中国の文化や中国人に対しての理解を深めることができます。中国語学習の最初の一歩に最適な講座です。
企業サイトはこちら:https://www.glova.co.jp/
株式会社WizWe

習慣化を得意としていて、なかなか効果が出にくいとされるe-learningを続けられるようにサポートするというのが特徴です。受講する人はアプリ上で、自分の進捗状況を確認できるだけでなく、習慣化サポーターとのコミュニケーションも可能です。習慣化サポーターからフォローコメントが届くので、挫折しにくい仕組みがあります。
・eラーニング+オンライン会話レッスン
eラーニング(超速中国語)とオンラインレッスン(ネイティブ講師)がセットになったコースです。
超速中国語は最新の脳科学と中国語習得理論を組み合わせてうまれた中国語トレーニングシステム。中国語検定4級レベルを65時間程度で合格することが可能です。(通常120~200時間)
超速中国語でインプット型の学習を行い、オンラインレッスンでアウトプット型の学習を行うことで、効果的に学ぶことができます。
企業サイトはこちら:https://wizwe.co.jp/
the courage(カレッジ)合同会社
中国語政府公認試験HSK&HSKibtの認定校the courage(カレッジ)では企業向けの中国語研修も提供しています。中国語を教えるのではなく「効果的な学習方法」「時間確保」「学習の継続」の3つをプロのコーチが1人1人に寄り添って徹底的にサポートすることで圧倒的な中国語力の伸びを実現し続けている中国語コーチングです。日本人・ネイティブのコーチがいるので安心で、1クラスは1~5名を推奨しています。元海外人事担当のキャリアコンサルタントが丁寧にニーズをヒアリングしてから研修内容を提案します。
※用意されたコースはなく、ニーズに合った研修が可能。
中国駐在が決まった方への短期集中の中国語コーチングから、その後のフォローアップまでプロコーチが徹底サポートするというのが特徴
マンツーマンの他、グループコーチング(2~5名)の対応も可能、オンラインで完結するので全国どこにいても受講ができます。
企業サイトはこちら:http://courage-lang.com/
企業向け中国語研修プログラムを開始する前に確認しておきたいこと
どれくらいカスタマイズが可能か?
ここまで確認してきた通り、各社それぞれのニーズがあるので、そうしたニーズに対してどれくらいカスタマイズが可能かということを確認しておきましょう。
カリキュラムがきちっと決まっているのは魅力的ですが、その分融通が効かずに効果が限定的になるということも多いためです。
体験レッスン/模擬レッスンなどが可能か?
実際のレッスンを受けることなく判断するのは難しいので、体験レッスンや模擬レッスンが可能かを確認しましょう。人事部門の社員が受けてみるというケースもあれば、対象となる社員に受けてもらい、その後インタビューを行うなどの方法も可能です。
休んだ場合のフォローなどはあるか?
こちらも画一的な対応であればお休みのフォローが無いということもあるので、事前に確認しておきましょう。急な仕事や出張でレッスンに出れないということはよくあります。そうした場合の対応は研修導入にあたり非常に重要なポイントです。
プロに相談してみる
中国語研修導入を考えているけれど、どのような選択肢があるかがわからない、あるいは判断が難しいという場合はぜひプロに相談してみてください。
無料でオンラインでの相談・カウンセリングが可能です。
法人研修導入の相談先:the courage
【中国語研修導入の教科書】PDFを無料でプレゼント
\知りたいことが全部わかる!/
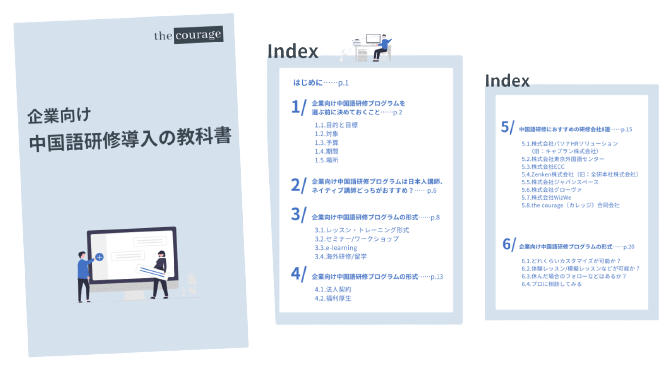


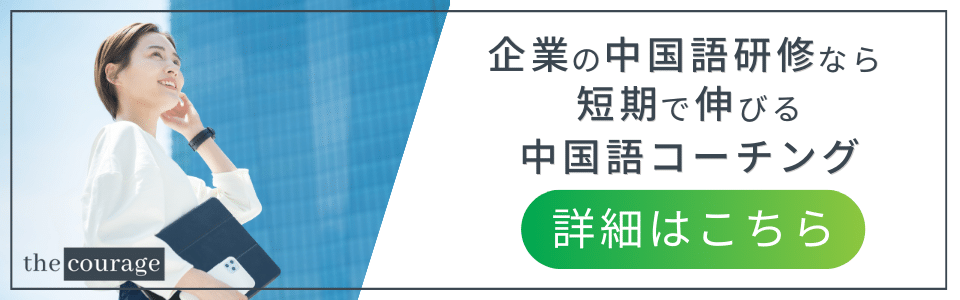
-1024x475.png)









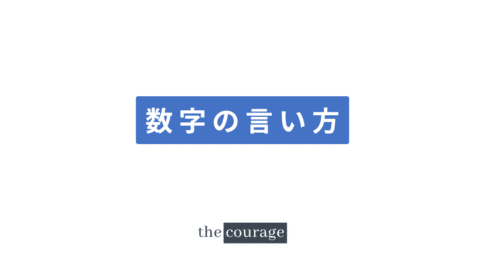

-485x256.png)

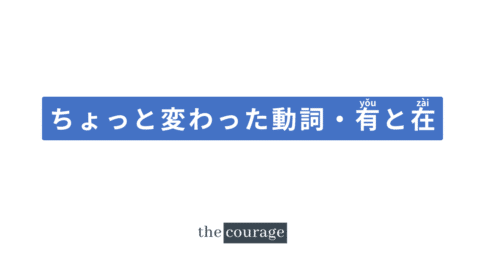


-300x169.png)

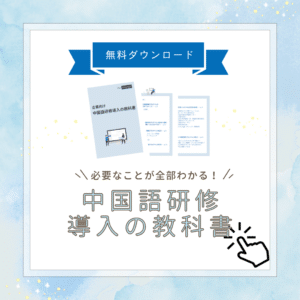
the courage 伊地知
キャリアコンサルタント(国家資格)
三菱重工業株式会社にて海外人事担当として100人以上の海外赴任をサポート、語学研修導入を経験した後、日本で最初の語学コーチングスクールにて700名以上の受講生の語学学習をサポート、コーチ育成、中国語コーチング立ち上げを行う。2019年、語学学習を通じて一人一人が「自分の人生を自分で決める勇気」を持てるようにという想いでthe courage(カレッジ)を設立。雑誌「聴く中国語」への寄稿、大手英語コーチングスクールのコーチング監修など実績多数。(旧HSK10級、現HSK6級)